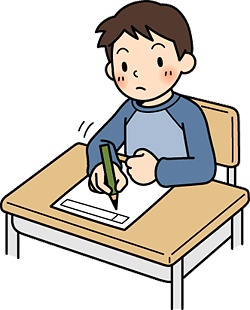 |
公認会計士試験 合格体験記 |
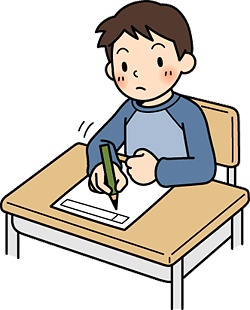 |
公認会計士試験 合格体験記 |
|
「努力して繁栄を 努力して勝利を 努力して建設を」−母校創価大学の第24期生の卒業式(1998年3月)での創立者のスピーチです。何事も努力から。公認会計士試験のような国家資格を勝ち取るには努力が必要です。どうすれば「努力」を持続できるのか。その秘訣は、「なんのため」という動機ではないかと思います。
高校1年の頃、大学の先輩方から国家試験の合格体験を聞かせていただく機会がありました。その時に、公認会計士という資格を知り、元々理数系の私にはに、向いている資格だと思いました。何故、資格にこだわったのでしょうか。それは、国籍が韓国であったという事につきます。在日韓国人二世であった私は、小さい頃から、多くの在日韓国人の方と付き合う機会がありました。そうして、日本で生活する以上、在日韓国人ということが有利に働くことは殆どなく、むしろ、不利なことだらけであるとの思いを感じていました。「自分は普通の日本人とは違う。そうであるなら、何か差別されない武器を持とう」と受験を決意したのです。自分が書いた合格直後の体験記では、その当時の思いを下記のように綴っていました。 「数十万人いるといわれる在日韓国人の世界の中で、自分が何か有為な仕事がしたい。在日韓国人の社会問題は山と積まれている。何とかできないものか、そのためには社会に実証を示し、認められるような人材になっていかなくてはならない。社会に実証を示すための武器として公認会計士になろう。自分にとっての公認会計士試験に合格することは、スタートラインにたつことであり、自分の本当の勝負は、会計士になって社会に実証を示し、韓国人としてどう生きていくかにあるのだ。」
卒業後の10年間、外資系の会計事務所で働かせていただきました。仕事の合間での会話で、現役合格でも難しいとされる試験によく3年で合格できたと賛嘆されることがありました。しかし、私だけが抜きんでてたわけではなく、「3年合格」は1期生から築いて下さった創価大学の伝統でありました。受験勉強の最期には、自分の人生のためというより、3年合格の伝統を絶やしてはいけないとの思いがほとんどでした。そして、落ちたら、応援して下さった皆さんに申し訳ないとの思いが強かったものです。
世間の多くの人が、生活を賭けて挑戦している試験に、若輩者が合格の仲間入りをするのは、決して楽ではありませんでした。専門学校の模擬試験でも、合格圏内といわれる上位の成績がなかなかとれません。その頃、自分自身に言い聞かせたことは、相撲の世界で譬えていうなら、ともかく、土俵に上がって勝負させて下さいということでした。つまり、十両以下にいる限り、幕内優勝できる可能性はゼロですが、前頭の10枚目でも優勝する可能性はあるという事です。球技スポーツでいうなら、先発出場とまではいかなくても、ベンチ入りのメンバーに選ばれてさえいれば、活躍できるチャンスはあるという事です。私の模擬試験の成績は、合格ラインへの瀬戸際なものが多かったものです。大学の諸活動等で、ともかく、勉強の絶対量が足りない自分にとって、最低限の勝負ができる実力をつけなければと勉強にもがいたものでした。
大学入学当初から、公認会計士試験を志していた私でしたが、最初から焦らない方がいいとの先輩の指導から、1年の秋頃までは、高校まで所属していたハンドボール部のクラブ活動を続けたり、滝山祭等の大学行事にも積極的に参加しました。大学は、受け身的な高校教育と違い、あくまでも自由な能動の世界です。国家試験は、勉強が大変だと、入学当初からエンジンをかけて勉強をはじめるより、自分はなんのために生きるのか、との生涯の命題の土台を築く時が大学入学当初ではないかと思います。私にとっても、入学当初の友人との語らいや、先輩からの指導は、厳しい受験生活を乗り越えられる大きな礎となったものです。 明治時代の思想家内村鑑三の言葉に、「経済の背後に政治あり、政治の背後に社会あり、社会の背後に道徳あり。」とあります。バブル経済後の不景気の元凶は、経済そのものではなく、人間精神の衰退であるといえます。「人間主義の経済の確立」これこそが、創大生としての公認会計士である私の使命であると捉えています。
会計事務所での10年の経験の後、更なる経験を積もうと外資系のコンピュータソフト会社で4年間働きました。そこでは、会計管理分野での情報システム導入のコンサルティング業務が主な仕事でありました。これからの情報社会、コンピュータの利用が益々重要になってくると思って転職いたしました。その会社では、公認会計士としての経験が大きく役に立ち、ある自分の携わった仕事では、成功事例として日本経済新聞に全面掲載されるという実績を作ることができました。
公認会計士試験に合格して15年が経った平成10年、広川公認会計士事務所を開業しました。また、公認会計士だけの業務に止まらず、情報システムの整備、世界交流を目指して、HBS
(Hiro Business Solutions )
を設立いたしました。これまでに、仕事等を通じて世界10数カ国数十都市を訪問させていただく機会がありました。こうした経験を積めた背景にも、公認会計士という資格を有していたという感謝があります。今後も、資格をどのように使うのかとの「なんのため」との自らへの問いかけを忘れず、「努力」という座右の銘を胸に、頑張ってまいる決意です。 拙い体験ではありますが、少しでも皆さんのお役に立てれば、幸いです。
|